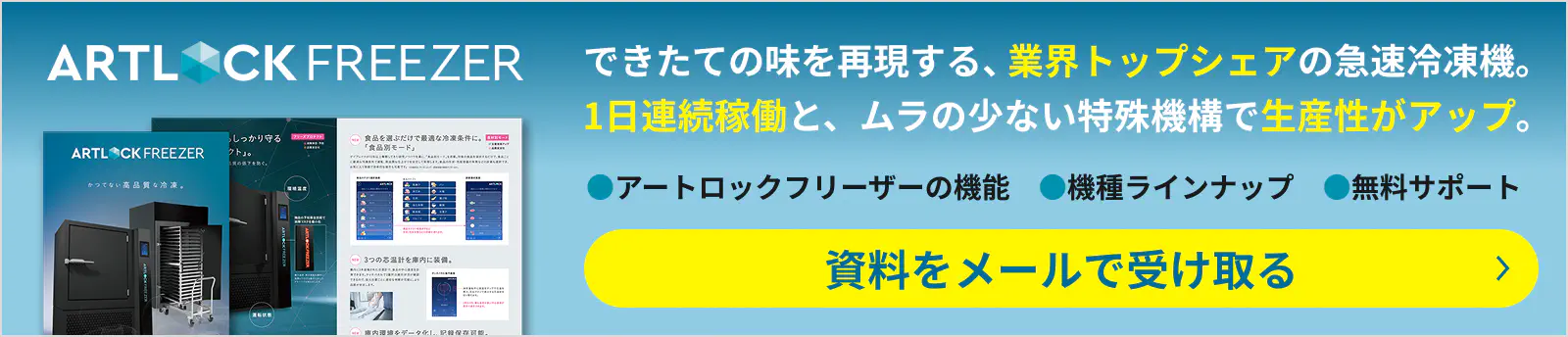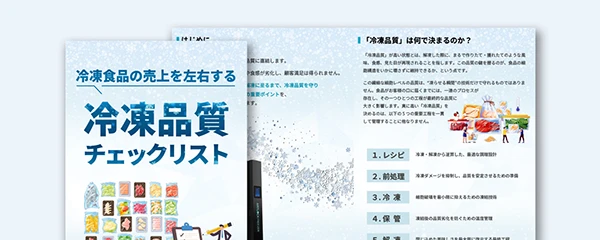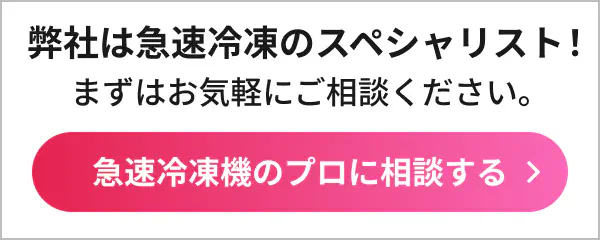セントラルキッチンとは?飲食店の店舗運営に活かすメリットや仕組み、導入方法を解説

こんにちは。急速冷凍機の厳選比較サイト「春夏秋凍」のライターチームです。
セントラルキッチンは、調理場所を集約し、店舗運営を効率化する仕組みです。コスト削減や料理の品質の維持、店舗の拡大など、さまざまなメリットがあります。ただし、食品の衛生管理が難しい点には注意が必要です。この記事では、セントラルキッチンを店舗運営に活かすメリットを解説します。店舗運営の課題を解決する方法も解説するので、ぜひ参考にしてください。
目次
セントラルキッチンとは?基本概念と仕組み
セントラルキッチンとは、調理に必要な工程を1カ所にまとめた施設です。メニューの製造や加工などを行い、冷凍や冷蔵、チルドで保存して各店舗に発送します。店舗では、加熱をはじめとした簡単な仕上げのみで、料理の提供が可能です。セントラルキッチンでの調理は、パンや麺類だけでなく、生鮮品をはじめとした、さまざまな料理に対応しています。
※関連記事:セントラルキッチンとは?仕組みや調理法(チルド・冷蔵・冷凍)について解説!
セントラルキッチンを店舗運営に活用するメリット
セントラルキッチンは、飲食店の運営を効率化できます。ここでは、店舗運営に活用するメリットを解説します。
コスト削減につながる
セントラルキッチンは、運営にかかるコストを削減できます。仕入れや調理に必要な人件費を抑えたり、食材の大量仕入れによる原価の削減をしたりすることが可能です。調理に必要なスペースや、調理の設備や器具なども最小限に抑えられます。また、各店舗に食材を配送するコストを削減できるため、効率的な運営につながります。
※関連記事:飲食店のFLコストとは?理想の比率と削減のための対策を紹介
料理の品質を安定して維持できる
セントラルキッチンで調理をまとめると、料理の品質が安定します。調理のノウハウや工程を標準化することで、属人化を防止できるためです。従業員の調理の腕や店舗の設備などに左右されないため、味のムラを避けられます。質の高い料理を提供し続けることで、顧客の満足度を高められるでしょう。
効率的な運営により店舗を展開しやすくなる
調理に必要な人材やコストを抑えることで、運営の効率が向上し、店舗を展開しやすくなります。調理の設備やスペースを最小限に抑えて、出店のコストも削減できます。たとえば、賃料の高額な場所や、小さな物件での開業が可能です。
※関連記事:飲食店の人時生産性を上げるには?有効な手段や注意点を解説します。
多店舗展開によってブランドを向上させられる
多店舗展開をすると、飲食店のブランドイメージを広げられます。消費者の目につく機会が増えて、多くの場所でブランドが認知されるためです。セントラルキッチンによって料理の品質を維持できるため、リピーター獲得にもつなげられます。ブランド独自の強みで差別化でき、競争の激しい市場でも消費者に選ばれやすくなるでしょう。
※関連記事:飲食店が多店舗展開するメリット・デメリットを紹介!成功のポイントは急速冷凍機
セントラルキッチンを店舗運営に活用するデメリット
セントラルキッチンは、食品の衛生管理や配送の際の品質維持が困難です。ここでは、店舗運営に活用するデメリットを解説します。
徹底した衛生管理が難しくなる
セントラルキッチンで調理したものは、調理から配送までの時間が空くため、衛生管理を徹底しなければなりません。料理の衛生管理では、「加熱」「冷却」「保存」の3工程を徹底する必要があります。温度や湿度、カビや細菌などの影響を受けるため、食中毒のリスクを防止することが大事です。それぞれの段階で、温度と時間を記録して食材を管理しましょう。
※関連記事:【食品等事業者は必須】HACCPの導入と急速冷凍を使う理由とは
初期投資とランニングコストがかかる
セントラルキッチンを利用する際は、初期費用がかかります。調理設備や器具のほか、土地や物件、運搬車も必要です。また、設備を運営する際の、水道光熱費をはじめとしたランニングコストもかかります。冷凍や冷蔵、チルドに使用する設備も必要なため、費用を回収する試算を立てることが大事です。
※関連記事:セントラルキッチンの費用相場と導入を成功させるコツを解説
店舗に配送する際に品質を維持しにくい
セントラルキッチンで調理したものは、配送する際の品質維持が難しくなります。食材の鮮度を保つために、品質の劣化を防止しなければなりません。たとえば、温度管理や包装後の高温での殺菌処理などの工夫が必要です。食品加工設備の導入をはじめとした、食品の品質を維持するノウハウの構築も求められます。
店舗ごとの柔軟なメニュー展開が難しい
セントラルキッチンを導入している場合、仕込みや調理は1か所で行うので、複数の店舗で共通したメニューを提供することがほとんどです。そのため、ご当地食材を使ったメニューや季節にあわせたメニュー、顧客の好みにあわせたメニューなど店舗独自の柔軟なメニュー展開は困難です。
セントラルキッチンを用いた店舗運営の課題
セントラルキッチンの運営には、食品ロスや食中毒などのリスクがあります。ここでは、店舗運営の課題を解説します。
食品ロスの増加につながる
セントラルキッチンで調理したものは、一般的な飲食店と違い、注文に応じて調理をしないため、食品ロスになる可能性が高まります。大量に調理したものは代用できないため、注文されない場合、廃棄につながります。人件費や光熱費などもかかっているため、食品ロスによるコストを管理しなければなりません。
※関連記事:食品製造における廃棄ロスと賞味期限に対する施策
※関連記事:廃棄ロスにかかる費用はいくら?食品ロス削減への対策もご紹介
食中毒が広まる際のリスクが大きい
セントラルキッチンで調理されたものが食中毒の原因となった場合、製造工場だけでなく、すべての店舗の運営を停止しなければなりません。1か所での調理は効率的ですが、問題が起きた際は広範囲に影響を及ぼします。営業を再開する場合は、再発防止措置を取らなければなりません。
セントラルキッチンの課題解決には急速冷凍がおすすめ
セントラルキッチンの課題を解決するには、急速冷凍がおすすめです。調理したものをできたての状態のまま凍らせるため、食品の品質を維持できます。通常の冷凍技術では、食材の細胞が破壊され、味が落ちる可能性が高くなります。その点、急速冷凍は細胞の破壊を最小限に抑えられるため、元の状態に近づけて解凍できます。
急速冷凍によって、食材の鮮度を維持でき、長期間保存もしやすくなります。使いたいときに使いたい分だけ解凍すればいいので、食品ロスや食中毒のリスクを抑えることが可能です。繁忙期や閑散期などを考慮して、食品の計画生産もできます。工場や厨房の稼働率が平準化し、業務時間・人件費の削減につながるため、急速冷凍を導入するメリットは大きいといえます。
※関連記事:セントラルキッチンでの急速冷凍の活用方法とは?品質が落ちない【メリット・デメリット】
※関連記事:急速冷凍機とは|種類やメリット・選び方・おトクな導入方法も解説
セントラルキッチンの主な保存方法
セントラルキッチンには、チルドや冷蔵、冷凍といった保存方法があります。ここでは、主な保存方法について解説します。
※関連記事:急速冷凍技術とは?メリットや急速冷凍機の種類、急速冷凍機の選び方を解説
チルド
チルドは、0〜5度の温度帯で保存する方法です。調理したものは厳密な温度管理をし、冷蔵状態で保管します。衛生的な環境で保管すれば、1〜5日の保存が可能です。セントラルキッチンで盛り付けもできますが、配送する際に食品の温度を一定に保つことが求められます。
※関連記事:【製造・飲食業向け】チルド食品とは?冷凍との違いや特徴を解説
冷蔵
冷蔵は、0〜10度の温度帯で保存する方法です。品質を維持するために、冷蔵庫で冷却を続けて保存します。食品ごとに温度管理の範囲が定められており、賞味期限が短い点がデメリットです。在庫管理や厳密な温度管理が必要なため、セントラルキッチンを稼働し続けなければなりません。
冷凍
冷凍は、マイナス18度以下の冷凍庫で保存する方法です。チルドや冷蔵よりも保存期間が長く、簡単に在庫管理ができます。配送先で解凍する必要がありますが、急速冷凍を活用すれば、遠方の配送地域でもできたての料理を提供可能です。急速冷凍は食品の味だけでなく、栄養価や食感なども維持できるため、セントラルキッチンの導入におすすめです。
※関連記事:【冷凍で長持ち】野菜の保存方法で気をつけるべき3つのポイント
※関連記事:急速冷凍とは?温度や冷凍時間の定義、メリット、適した食品まで解説
セントラルキッチンの調理方法
セントラルキッチンの調理方法として、新調理システムが注目されています。大きく分けて「クックチル」「真空調理」「クックフリーズ」の3つについて解説します。
クックチルシステム
クックチルシステムは、食品を加熱調理した後、90分以内に中心温度を3℃以下まで急速冷凍し、0〜3℃の低温で保存する調理方法です。保存期間は最大5日間で、微生物が繁殖しやすい10〜60℃を短時間で通過するため、食中毒の原因となる細菌の増殖を抑制できます。
クックフリーズシステム
クックフリーズシステムは、加熱調理後、30分以内に凍結させ、その後90分以内に中心温度を-5℃以下まで冷凍、最終的には-18℃まで急速冷凍するシステムです。最大で8週間程度の保存が可能で、食事を提供するタイミングで再加熱します。
真空調理法
真空調理法は、下処理した食材を調味料と一緒に真空パックしたあと、95℃以下の低温加熱・冷却する調理方式です。低温で加熱するため、素材の風味や栄養を損なわずに提供可能です。
セントラルキッチンを導入する手順
セントラルキッチンの導入は、手順を追って進めることが重要です。導入は、以下の手順で進めましょう。
- セントラルキッチンを導入する目的や課題を明確にする
- 導入の計画を綿密に立てる
- 土地と建物を選ぶ
- 必要な設備と人員を洗い出す
- 適切な人材の採用とトレーニングを行う
- 物流、配送システムを選定する
- テスト運用する
セントラルキッチンを店舗運営に導入する際のポイント
セントラルキッチンは、導入する目的やコストなどを決めることが必要です。ここでは、導入する際のポイントを解説します。
目的を明確にする
セントラルキッチンを店舗に導入する際は、目的を明確にしましょう。たとえば、コスト削減が目的である場合には、大量仕入れに対応できるものが必要です。店舗展開を目的とする場合、配送の時間やルートなども考慮しなければなりません。セントラルキッチンを導入する目的を明確にしたうえで、店舗運営に適切な方法で導入しましょう。
敷地や設備などを選定する
敷地や設備を選定し、配送の効率を考えることも大事です。店舗への配送や建物や設備を考慮した敷地など、将来の規模を想定する必要があります。セントラルキッチンを導入する前に、人員も確定しましょう。削減できる人員を見直し、管理システムや教育方法の立案などの計画を検討するとよいでしょう。
店舗のコストと比較する
セントラルキッチンを導入する際は、店舗運営のコストを比較する必要があります。初期投資のコストを考慮して、投資を回収できる綿密な計画を立てることが大事です。ただし、非現実的な計画を立てることは避けましょう。品質管理や作業員の教育なども考慮した、慎重な判断が求められます。
スモールスタートで立ち上げる
セントラルキッチンは、過剰な投資を避けるために、スモールスタートがおすすめです。売り上げや需要の増加を考慮して、段階的に規模を拡大するとよいでしょう。製造量に対応できる店舗が少ない場合、コスト増加や食品ロスなどのリスクにつながります。運営のノウハウが構築されてから、設備やスペースを見直すことが大事です。
専門家の助言を受ける
セントラルキッチンの導入は、一般の家庭用キッチンや飲食店の厨房とは異なる知識やスキルが必要です。知識がないまま進めると計画が頓挫する可能性があります。専門家やプロの助言を受け、効率的な運営方法を提示してもらったり、必要な手続きや対策をサポートしてもらったりしましょう。セントラルキッチンに関する豊富な知見や経験がある専門家やプロのアドバイスを聞くことが重要です。
まとめ
セントラルキッチンは、店舗運営の効率化につながります。コスト削減や品質の安定化、店舗拡大など、さまざまなメリットがあります。しかし、食品ロスや食中毒につながる課題があるため、店舗運営の際は注意が必要です。急速冷凍をはじめとした技術を活用し、味や栄養、食感などを維持する工夫が求められます。
デイブレイク株式会社は、急速冷凍機売上シェア1位の企業です。機械の販売だけでなく、冷凍用レシピの開発や、オペレーション構築など導入時のサポートも含めた提案をしています。冷凍に関して気になることがございましたら、お気軽にお問い合わせください。