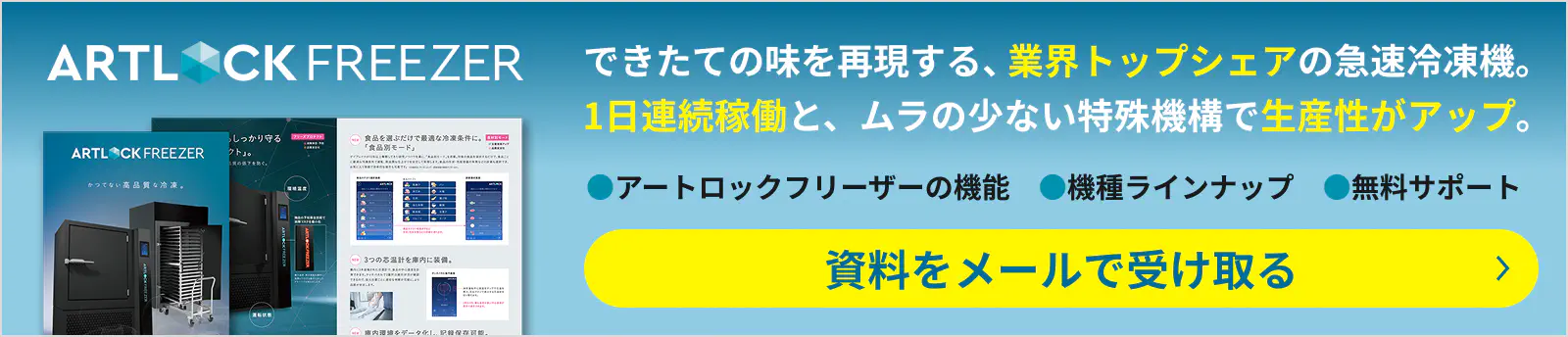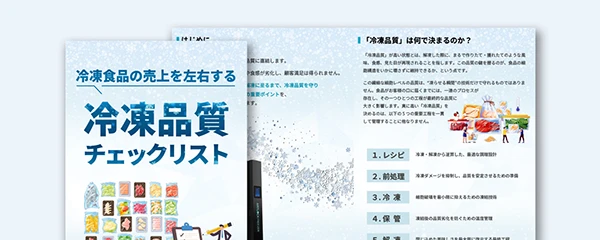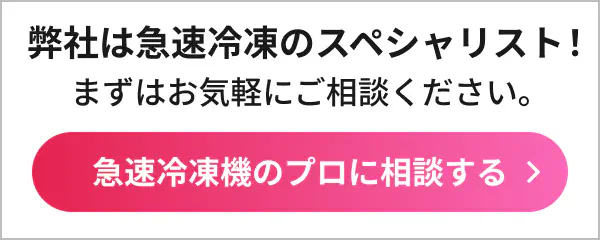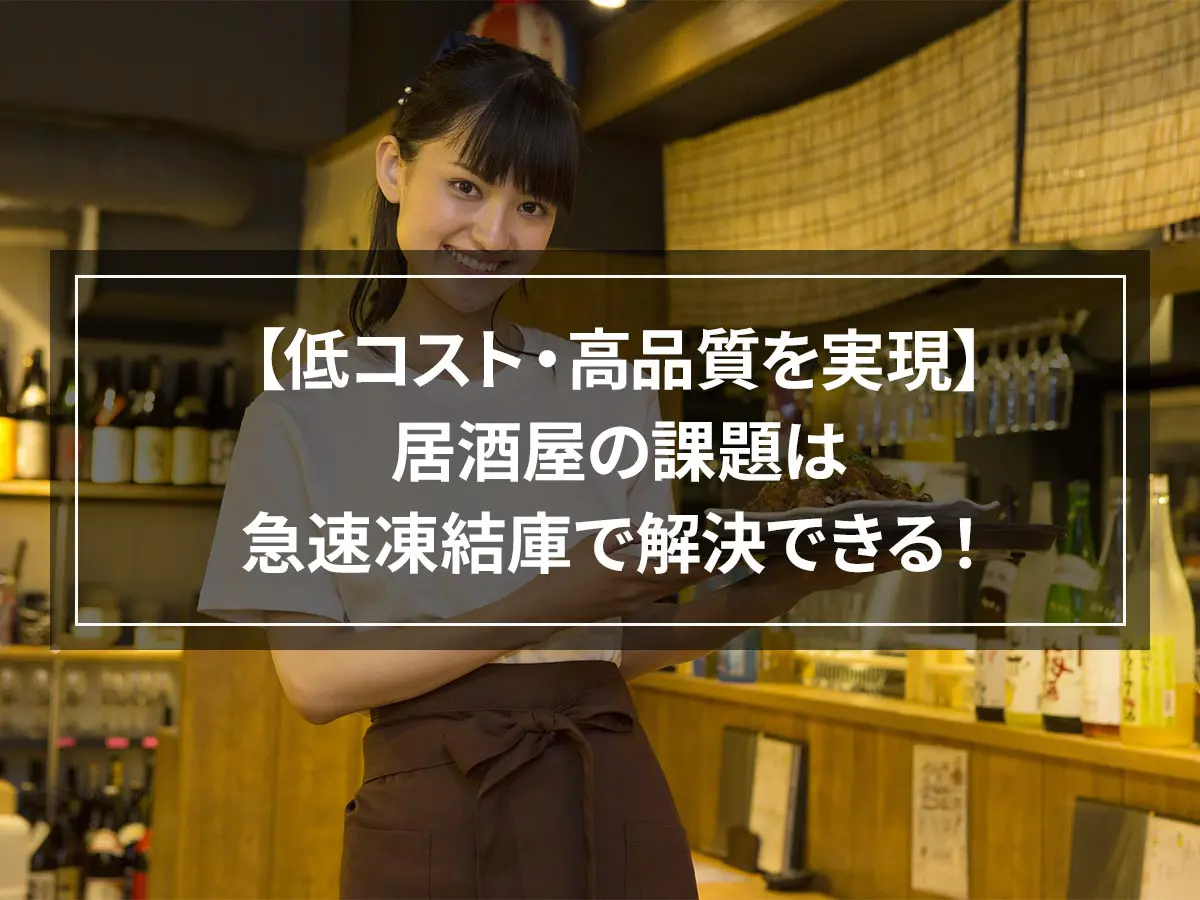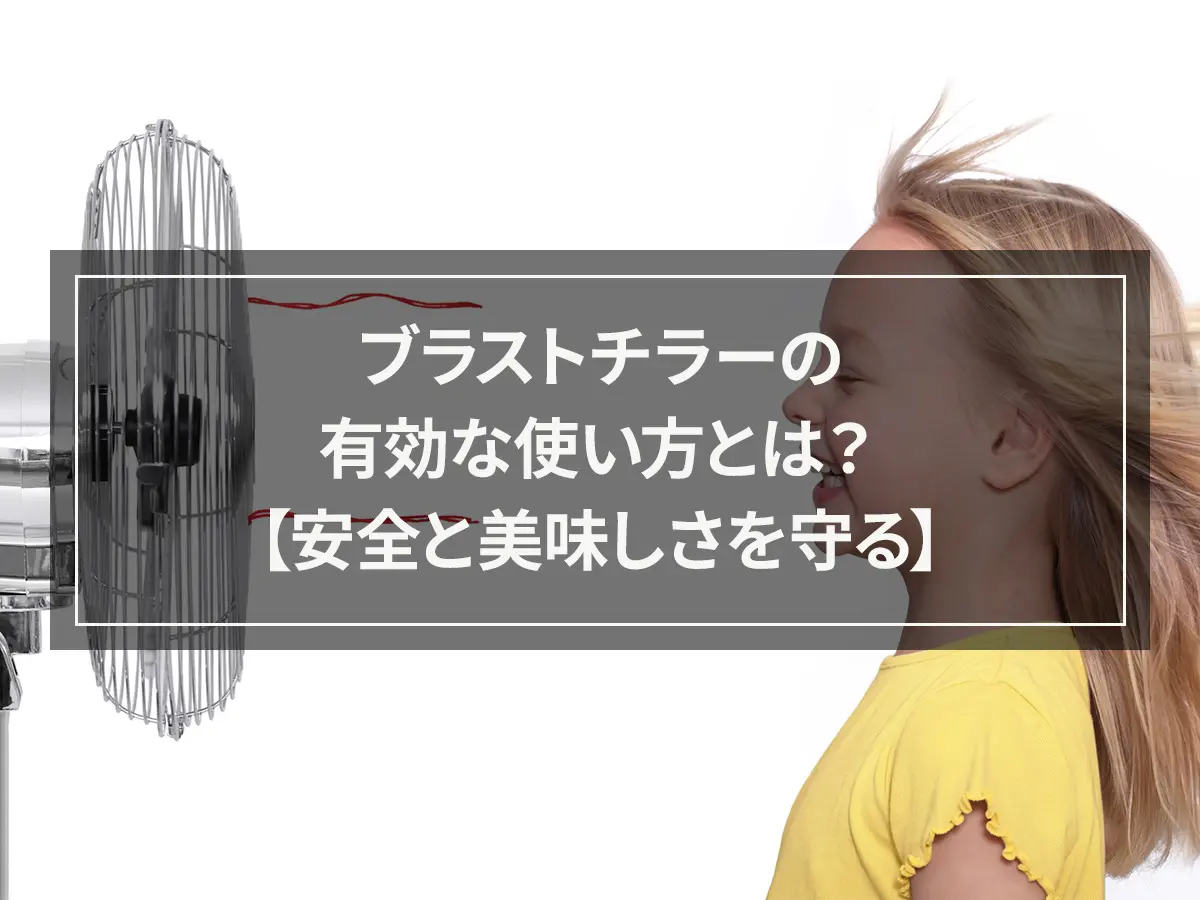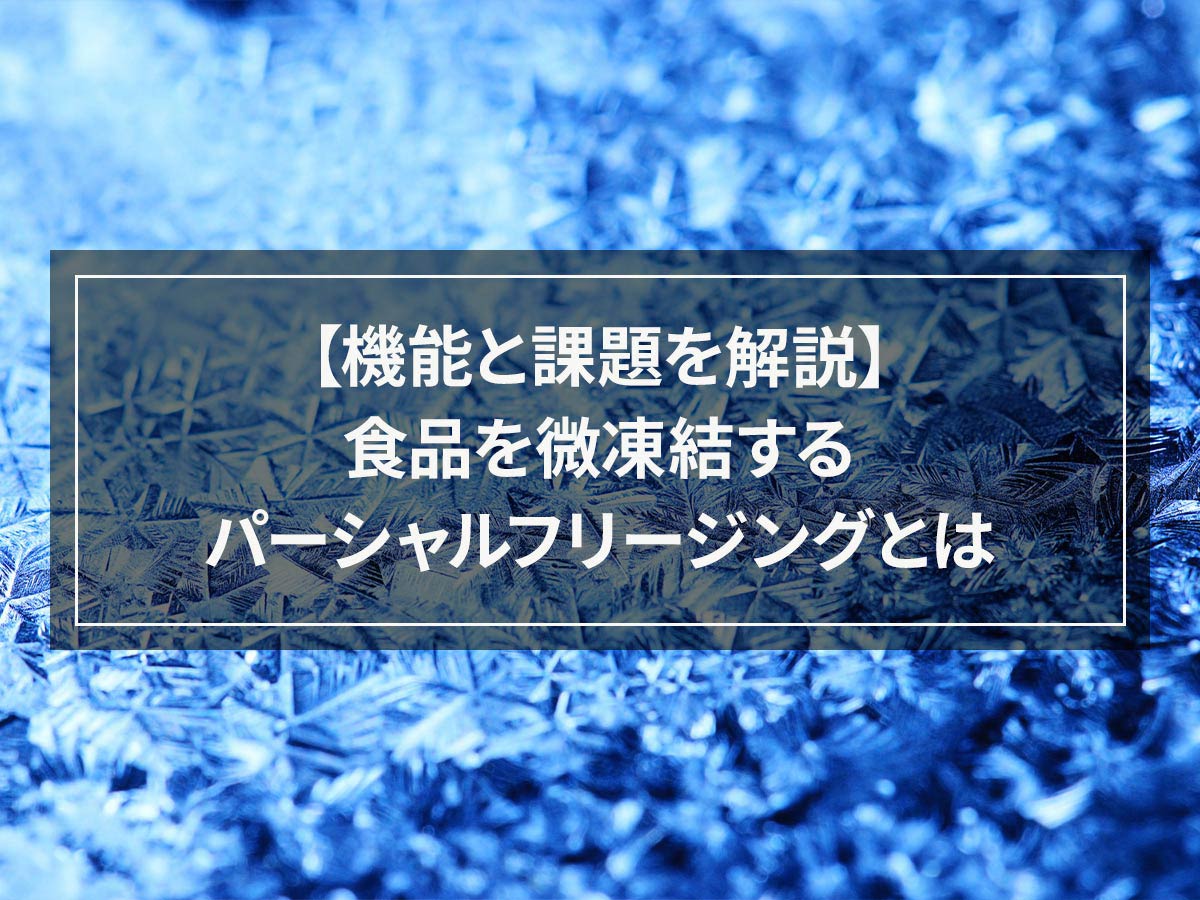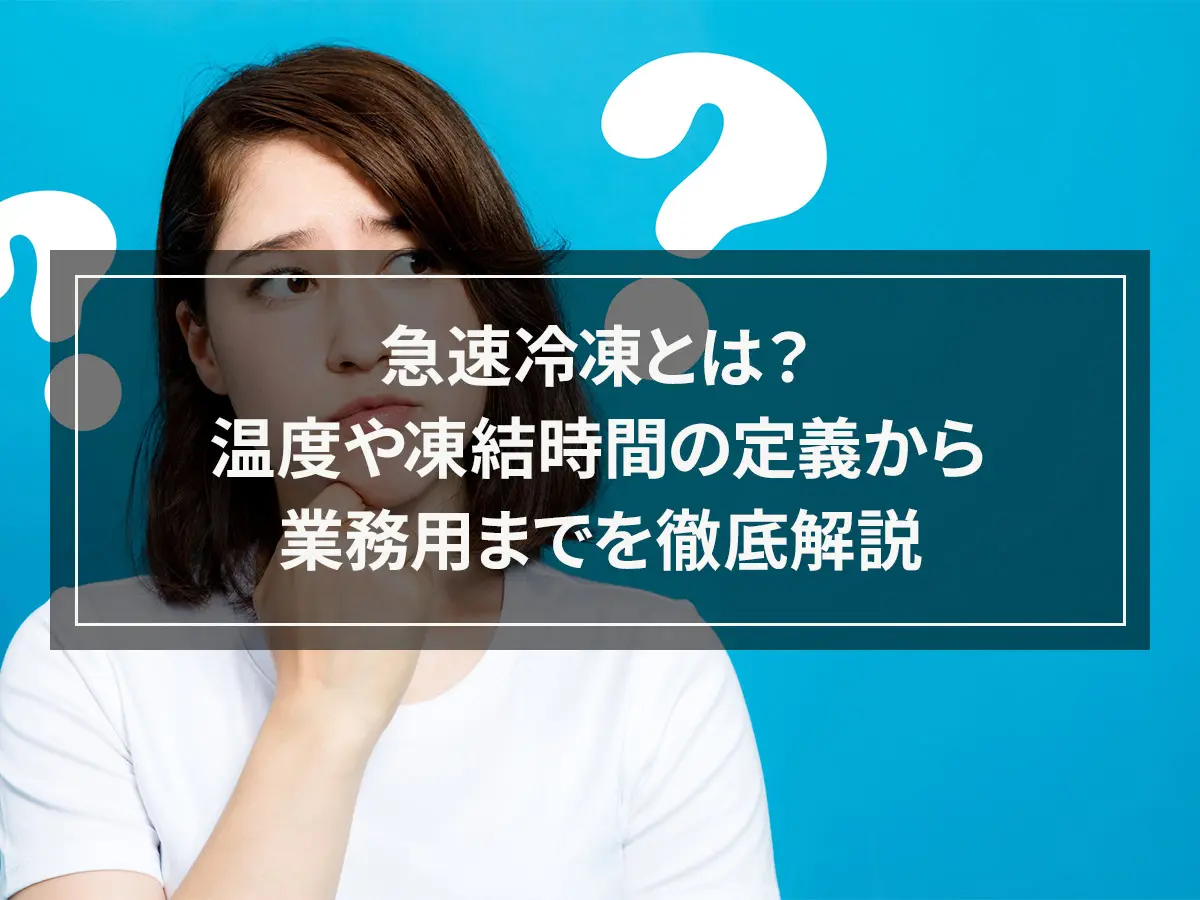冷凍食品の作り方・製造方法とは|販売するための基準やおすすめの急速冷凍機も解説

こんにちは。急速冷凍機の厳選比較サイト「春夏秋凍」のライターチームです。
冷凍食品はどのように作られるかご存知ですか?近年、冷凍食品の市場規模が伸び続けています。特に新型コロナウイルスの流行を機にその需要は大きく拡大し、消費者にも幅広く受け入れられるようになったと言えます。
では、長期間の保存が可能でおいしい冷凍食品はどのように作られるのでしょうか。この記事では、冷凍食品が満たすべき条件と、実際の作り方を解説します。ぜひ最後までご覧ください。
目次
冷凍食品とは?満たすべき4条件を紹介

冷凍食品として販売するには、食材・食品が以下4つの条件をすべて満たしている必要があります。
1.可食部のみ
冷凍食品の一つ目の条件は、冷凍する食品を可食部(食べられる部分)のみにすることです。消費者に代わって、冷凍食品業者が食材の洗浄やカット、魚の骨の除去などの前処理を行います。そのため、頭や内臓など食べられない部分を残したまま冷凍した魚などは、冷凍食品には含まれません。
冷凍食品を使うことで、飲食店の調理場や家庭などで不可食部の廃棄が発生せず、生ごみを軽減できるというメリットがあります。
2.急速冷凍する
二つ目の条件として、前処理済の食品を急速冷凍していることが挙げられます。急速冷凍とは、食品中の水分が氷の粒に変わる「マイナス1度からマイナス5度」の温度帯を、30分を目安に通過するように行う冷凍方法です。
食品の組織は凍結の過程で破壊されていくため、一般的なスピードで冷凍すると品質が劣化し、味や見た目、食感が悪くなることは避けられません。一方で、急速冷凍の場合、食品の品質が変化する前に素早く凍らせることができます。
※関連記事:急速冷凍とは?温度や冷凍時間の定義、メリット、適した食品まで解説
3.適切に包装する
三つ目の条件は、流通過程における食品の乾燥や形崩れ、汚れの付着などを防ぐため、適切な包装がされていることです。どんなに前処理と急速冷凍が適切に行われた食品でも、流通の際に変質してしまっては元も子もないでしょう。
また、包装には食品の情報が適切に表示されている必要があります。表示すべき内容は法律で定められており、品名や原材料名、調理方法、栄養成分などさまざまな項目があるため、漏れがないよう十分に注意しなくてはなりません。
4.マイナス18度以下での保存・流通
四つ目の条件は、輸送中に食品の品質が劣化しないよう、常にマイナス18度以下で保存・流通することです。なお食品衛生法では、有害微生物が繁殖できないマイナス15度を基準としています。しかし、マイナス15度とは「腐ることはない」温度であり、味や風味を維持できるわけではありません。
そこで一般社団法人日本冷凍食品協会では、より良好な品質を維持するため、自主基準として「冷凍食品自主的取扱基準」を定めました。マイナス18度以下とは、この自主基準で定められた温度です。なお、食品の国際規格であるCodex(コーデックス)でも、マイナス18度以下で管理するよう定められています。
工場での冷凍食品の作り方・製造方法

工場では、どのように冷凍食品が製造されているのでしょうか。前述の4条件を踏まえ、工場での製造過程を解説します。
1.食品・食材の前処理・調理
まずは、冷凍する食品が可食部のみになるように、食材の前処理と調理を行います。冷凍される食材は多岐にわたり、それぞれにとって最適な方法は異なるため、全食材に共通する前処理方法はありません。食材の前処理後には、食材同士の混ぜ合わせや、揚げる・蒸す・味付けなどの調理を行います。
例えば、魚のフライの冷凍食品を販売したい場合、以下のような作業を行います。
- 新鮮な魚を選定する
- 魚を洗浄する
- 頭・うろこ・ひれ・内臓・骨など、食べられない部分を除去する
- 切り身や三枚おろしなどにする
- パン粉を付けるなどして、揚げるだけの状態にする
また、冷凍野菜を製造する際は、ほとんどの場合「ブランチング」という加熱処理が行われます。ブランチングにより食品に付着している微生物を殺菌できるほか、野菜の酵素を不活性化させ、変色や変質を防ぐ効果があります。
2.食品の急速冷凍・検査
前処理と調理が済んだら、すみやかに食材・食品の急速冷凍を開始します。マイナス1度からマイナス5度の温度帯を速やかに通過するよう、一般的な冷凍庫ではなく、専用の急速冷凍機で冷凍しなくてはなりません。
調理・加工段階で異物が混入していないか、冷凍された食品・食材を検査することもあります。機械による重量検査や金属検査、X線検査などのほか、目視による検査も行われます。
3.商品の包装
続いて、冷凍された食品・食材を包装します。どのような包装が適切かは商品によって異なるため、それぞれにとって最適な包装を見極めなくてはなりません。真空包装やパウチ袋、プラスチックトレーなど様々な包装のなかから、食品・食材の特徴や形状に合ったものを選定することが大切です。
前述のとおり、包装には商品に関する情報が適切に表示されていなくてはなりません。情報に漏れや誤りがないかを、あらかじめチェックしておきます。
4.温度管理のもと保存・流通
包装まで完了したら、徹底した温度管理のもとで保存・流通を行います。食品・食材の品質をキープするにはマイナス18度以下での保存・流通が不可欠なため、温度帯には常に配慮が必要です。
工場ではマイナス18度以下で保存できていても、輸送の段階で温度が上がってしまうと、細菌の繁殖や食品の酸化が進んでしまうかもしれません。このような事態を避けるためにも、最適なコールドチェーン(生産から消費までの流れを低温かつ最適な温度管理のもと行うこと)の構築が求められています。
※関連記事:冷凍食品の安全性を保つ製造工程とは?規格基準や実際の手順を解説
冷凍食品の規格
冷凍食品は、製造工程によって規格が設定されています。代表的な規格と製造工程の特徴を解説します。
加熱後摂取冷凍食品
加熱後摂取冷凍食品とは、食べる時に加熱が必要な冷凍食品です。電子レンジや湯せんなどで温めるものが該当します。加熱後摂取冷凍食品のなかにも2種類あり、凍結前に加熱されたかで分けられます。「凍結直前加熱」は、凍結させる直前に加熱されたものです。フライドポテトやエビフライなどの揚げ物が該当します。
一方の「凍結直前未加熱」は、凍結させる直前に加熱されていないものです。また、調理時に加熱が必要な冷凍魚介類もこのカテゴリに含まれます。
無加熱摂取冷凍食品
無加熱摂取冷凍食品とは、食べる時に加熱しなくても問題のない冷凍食品です。冷蔵庫で解凍して食べるケーキや果物などが該当します。解凍前に加熱したかではなく、食べる前に加熱するかで分けられる点に注意しましょう。
生食用冷凍鮮魚介類
生食用冷凍鮮魚介類とは、生食用に凍結させた切り身やむき身の鮮魚介類です。刺身や寿司ネタなどが該当します。製造時に加熱はされず、食べる時にも解凍さえすれば加熱は必要ありません。厳密な加工基準があり、鮮度のよいものを原料に使用する必要があります。また、包装容器に入ったものでなければいけません。
※関連記事:【冷凍食品の規格基準とは】製造販売に必要な条件と急速冷凍機
冷凍食品の製造に求められる急速冷凍機の性能は?
ここまで冷凍食品の一般的な製造手順をご紹介しました。冷凍食品を製造する際に必要な設備の中でも特に重要なのが急速冷凍機です。
では、急速冷凍機はどのようなポイントで選定すべきなのでしょうか。
ここから急速冷凍機の選定において重要な「品質」、「コストパフォーマンス」の要素についてご紹介します。
1.品質
1つ目の要素は品質です。冷凍食品の品質は急速冷凍機の性能によって大きく異なります。解凍後の品質を上げるには①凍結スピードの速さ、②食材へのダメージ(乾燥・酸化など)の大きさがポイントです。
凍結スピードが速いと細胞の損傷を抑えることができ、解凍後の品質が高くなります。かと言って凍結速度が速くとも、乾燥・酸化といった食材へのダメージが入ってしまうと変色、臭みなどの品質劣化が起こってしまいます。そのため、凍結スピードが早く、食材へのダメージが小さい急速冷凍機が最適です。
2.コストパフォーマンス
2つ目の要素はコストパフォーマンスです。品質が高いからといって、イニシャルコスト・ランニングコストが高すぎるとその分商品の価格に転嫁する必要が出てしまいます。
特に日常的に購入する冷凍食品であればあるほど価格が上がってしまうとリピート購入に繋がらず、その結果として利益を生み出すのが難しくなってしまいます。そのため、コストパフォーマンスの高い急速冷凍機を選定することも非常に重要です。
※関連記事:急速冷凍機とは|種類やメリット・選び方・おトクな導入方法も解説
冷凍食品の製造にアートロックフリーザーが最適な理由

冷凍食品製造のための急速冷凍機でおすすめの機種は「アートロックフリーザー」です。以下で、アートロックフリーザーの魅力を解説します。
急速冷凍で味を落とさない
従来の急速冷凍機では、一方向から強い冷気を当てて冷凍していたため、冷凍ムラや食品の乾燥、身割れなどの品質劣化は避けられませんでした。一方、アートロックフリーザーでは、微細な冷気を庫内に充満させる特殊冷凍技術を用いており、食品にダメージを与えません。
乾燥や変色、ドリップなどを防ぎ、出来立てのおいしさと見た目をキープしたままの冷凍が可能です。飲食店や食品メーカーなど多数の食品会社でアートロックフリーザーが導入されています。ミシュラン獲得の飲食店でも導入されていることから、その実力は確かなものだと言えます。
コストパフォーマンスが高い
アートロックフリーザーには、自動制御が搭載されています。食材の種類や温度・投入量に合わせて最適な冷凍設定に自動調整されるため、省エネルギーで効率的な急速冷凍が可能です。イニシャルコスト・ランニングコストどちらも抑えて導入・運用ができます。
また、システムに負荷がかからない運用を自動で行うため、無理な運転による故障リスクが軽減され、修理コストの削減も期待できるでしょう。
アートロックフリーザーの導入・活用事例
急速冷凍機であるアートロックフリーザーは、実際に店頭でも使用されています。2つの導入事例を解説します。
スーパー「ダイエー」
関東・近畿で約200店舗を展開するスーパー「ダイエー」では、アートロックフリーザーを導入しています。導入以前から、高い鮮度を保ち、製造から購入後まで商品の劣化を防ぐ方法を模索していました。
機材の検討を進め、細胞を傷めることなく新鮮さや食感を保てるアートロックフリーザーの導入を決めました。導入後には「冷凍dai革命」という新たな冷凍食品シリーズを展開し、「高品質かつおいしい」商品であると伝える店頭プロモーションを積極的に実施しています。
※関連記事:スーパー・小売店が急速冷凍機を導入するメリットと活用事例をご紹介
洋菓子店「パレット」
滋賀県で地元住民に愛される洋菓子店「パレット」では、看板商品のパイをはじめ焼き菓子の品質向上と生産効率化を目指し、アートロックフリーザーを導入しています。パレットでは以前から急速冷凍機を導入していたものの、解凍後に食感や風味が損なわれてしまう問題がありました。
顧客満足度の向上を目指し新たな機材の導入を検討するなかで、アートロックフリーザーで凍結テストを実施しました。その結果、冷凍・解凍後も食感が損なわれず、1度冷凍したとは思えない再現性の高さを確認でき、導入を決断しました。また、前日に焼いたものを冷凍保存しても鮮度を保持できるため、生産性の向上も実現できています。
まとめ
冷凍食品として販売するためには、食品部位や冷凍方法、包装や流通管理などについて、定められた4つの条件を満たす必要があります。とりわけ、急速冷凍は食品の品質維持にとって重要な工程です。製造で使用する急速冷凍機の種類によって品質や保存期間なども大きく変わる場合があります。
冷凍食品の製造に使用する急速冷凍機を選定する際には妥協せず、最適なものを選びましょう。なかでも「アートロックフリーザー」は、食品・食材を素早く、出来立てのおいしさをキープしたまま冷凍することが可能です。アートロックフリーザーにご興味がある方は、ぜひ資料をご覧ください。